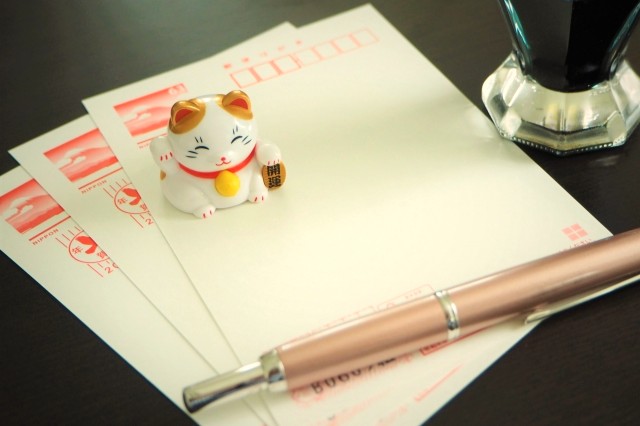
以前もらった年賀状や手紙、何となく捨てられずにしまいこんでいませんか?
特に年賀状は、送り主の名前や住所、家族写真まで印刷されているため「個人情報が見られないか心配」「安全な捨て方がわからない」という方も多いです。また、結婚・出産報告のはがきも捨てづらいですよね。
この記事では、個人情報に配慮して年賀状・手紙を捨てる方法を解説します。捨てるのに抵抗がある場合の処分方法や、おすすめの保管方法もご紹介しているので、ぜひ試してみてください。
目次
年賀状・手紙は「可燃ごみ」か「資源ごみ」
年賀状や手紙は、基本的に「可燃ごみ」か「資源ごみ」として扱われています。
一般的なごみと同じように回収に出せば処分できますが、自治体によっては独自の回収サービスを行っている場合もあります。例えば、東京都立川市では1月下旬から約1カ月間、市内各所に「はがき回収ボックス」を設置しています。お住まいの自治体がこのような取り組みを行っていないかどうか、ぜひチェックしてみてください。
また、資源ごみに出せるのはカラー印刷ができる「インクジェットはがき」以外のはがきに限ります。インクが定着しやすいようにコーティングされたはがきは再生利用できないためです。手書きのはがきなどは資源ごみとして、インクジェットはがきは可燃ごみとして処分しましょう。
【参考資料】
紙リサイクルの基礎知識|公益財団法人 古紙再生促進センター
はがきや封書のリサイクル|立川市
個人情報に配慮した年賀状・手紙の捨て方
年賀状や手紙には、ご自分の個人情報だけでなく送り主の名前や住所が記載されています。特に家族写真が印刷された年賀状は、個人情報保護の観点からも捨てづらいですよね。
年賀状や手紙を捨てる際は、次の方法で個人情報を保護しておくと安心です。
- 粘着テープでぐるぐる巻きにする
- 個人情報の部分を塗りつぶす
- シュレッダーやはさみで細断する
- 個人情報処分サービスを活用する
それぞれ具体的な方法を解説します。
① 粘着テープでぐるぐる巻きにする
家にあるもので簡単に対策したい方は、年賀状や手紙を束ねて粘着テープをぐるぐる巻くのがおすすめ。処分する量が少なくても多くても試しやすい方法です。テープは何重にも巻いて、見た目でわからないようにしましょう。
ただし、テープを巻くと資源ごみとして回収に出すことはできません。必ず可燃ごみとして出すようにしてください。
似た方法として、瞬間接着剤ではがきや手紙を貼り付けていくのもおすすめです。手間はかかりますが、より厳重な対策になります。どうしても見られたくないはがき・手紙がある場合に試してみるとよいでしょう。
② 個人情報の部分を塗りつぶす
処分する年賀状や手紙が少なければ、個人情報の箇所をペンやスタンプで塗りつぶすだけでも対策になります。塗りつぶしても資源ごみとして処分できるため、リサイクルに回したい方にもおすすめです。
ペンで塗りつぶす場合は、下が透けて見えないように黒い油性マジックを使いましょう。
「個人情報保護スタンプ」は、ランダムな文字列や濃い色のインクで個人情報をカバーするアイテムです。ぽんぽん押せるハンコ式や、広範囲を一気に消せるローラー式などさまざまな種類があります。1000円以下で買える小さなスタンプなので、使い勝手がよいものを探してみてください。
③ シュレッダーやはさみで細断する
個人情報が気になる紙類も、細かく切ってしまえば復元するのは難しいですよね。年賀状や手紙はシュレッダーやはさみで細断してしまうのもおすすめです。
処分する量が少なければ、はさみでも簡単。刃が複数枚ついた「シュレッダーばさみ」を使えば、より細かく切れます。500円前後で購入できるので、ぜひ試してみてください。
大量の年賀状や手紙を処分する場合は、この機会に家庭用シュレッダーを導入するのもよいでしょう。ご家庭に届くクレジットカードの明細書や自治体からの通知など、個人情報書類の処分にも使えます。
家庭用のシュレッダーは、手動式・電動式、または細断方法や大きさによってさまざまな製品があります。価格帯も1000~4000円前後と幅広いです。使用頻度や収納場所などを考えて、ご家庭にぴったりのシュレッダーを選びましょう。
④ 個人情報処分サービスを活用する
年賀状や手紙を含め、個人情報が記載された大量の紙物を一気に処分したい場合は、業者の個人情報処分サービスを利用するのもおすすめです。
個人情報処分サービスには、書類を丸ごと溶かす「溶解処理サービス」や、細断する「シュレッダーサービス」などがあります。処分したい書類を箱に詰めて発送するだけで利用できるうえ、処理後はリサイクルによって再生紙に生まれ変わるため、環境にも優しいです。
年賀状・手紙や書類以外にも、手帳や日記帳、不要な通帳なども一緒に処分できます。引越しや実家の整理など、個人情報の対策にあまり時間をかけられない場合にも便利なので、ぜひチェックしてみてください。
年賀状・手紙を捨てる際の注意点
個人情報への対策のほかに、年賀状や手紙を捨てる際に注意してほしいポイントは3つです。
- 捨てる前に相手の名前・住所に変更がないか確認
- 「お年玉付年賀はがき」は当選番号をチェック
- 郵便局の「はがき回収サービス」は廃止されている
それぞれを詳しく解説します。
① 捨てる前に相手の名前・住所に変更がないか確認
年賀状には、相手の最新の名前や住所が記載されています。年賀状を住所録の代わりにしている場合は、処分前に情報が変わっていないか確認しておきましょう。直近の年賀状や手紙とPC・スマホのデータを照らし合わせておくと安心です。
また、喪中のために年賀状のやりとりがなかった方や、引越しで住所が変わった方もいるかもしれません。大切な方の情報を抜け漏れなく把握しておくためにも、年賀状は2〜3年ほど保管するのがおすすめです。
② 「お年玉付年賀はがき」は当選番号をチェック
その年の「お年玉付年賀はがき」を処分する場合は、ぜひ当選番号をチェックしてください。賞品がもらえる可能性もあるため、確認せずに処分するのはもったいないです。
当選番号は、郵便局のホームページなどで確認できます。賞品への引き換え期間は当選発表から約6ヶ月です。賞品と引き換えた年賀状は返してもらえるため、その後に処分するとよいでしょう。
③ 郵便局の「年賀状回収ボックス」は廃止されている
以前、郵便局には使用済み年賀はがきの回収ボックスが設置されていました。しかし、個人情報保護の観点から現在は廃止されているため、持っていっても回収してもらえません。
未使用・書き損じの年賀状については、1枚につき手数料6円で新しい切手やはがきと交換してもらえます。喪中のために出せなくなった年賀状は無料で交換してもらえるため、お近くの郵便局の窓口で問い合わせてみてください。
年賀状・手紙の処分は縁起・風水に悪影響?
「相手からもらった年賀状や手紙を捨ててしまうと、縁起や風水としてよくないのでは?」
このように感じている方も多いかもしれません。
確かに、年賀状は風水でも縁起物とされています。しかし、お守りや破魔矢を1年限りで神社にお返しするように、風水における年賀状の効力もその年限りです。むしろ、風水では気の流れを重視するため、古い年賀状や手紙をいつまでも溜めているのは悪影響だともいわれています。
先にお伝えしたように、住所録として年賀状を使う場合は2~3年ほど保管しておくのがおすすめです。しかし、マナーやルールというわけではありません。風水や縁起のよさを重視したい方は、住所などを控えたうえで早めに処分するとよいでしょう。
捨てづらい年賀状・手紙は「お焚き上げ」もおすすめ
今はもういない方から届いた手紙や、遺品整理で出てきた年賀状の束などは、捨てるのに抵抗を感じますよね。捨てづらい場合は、どんど焼きやお焚き上げで供養すると縁起もよいうえ、気持ちの整理にもなります。
どんど焼きとは、1月15日の小正月ごろに行われる伝統行事です。正月飾りやお守りなどを神社や地域の広場などに持ち寄って、燃やして供養します。一方、定期的な祭礼として「お焚き上げ」を実施している神社・お寺もあります。
どんど焼きでは無料で供養してもらえる場合が多いですが、個別にお焚き上げを依頼する場合は「玉串料(御焚上料)」が必要です。年賀状や手紙のお焚き上げでは、数枚なら1,000〜5,000円、大量にある場合は5,000〜1万円が相場とされています。
ただし、どんど焼きやお焚き上げを行う寺社・地域でも対象とする品物は異なります。年賀状や手紙を受け付けているかどうか、事前に問い合わせておきましょう。お近くに対応している寺社がない場合は、郵送でのお焚き上げを受け付けている寺社や、民間のお焚き上げサービスも利用するのもおすすめです。
また、どんど焼きの場合は不特定多数の方が参加します。個人情報が漏れないよう、油性マジックや個人情報保護スタンプで該当箇所を塗りつぶしたうえで持ち込むようにしましょう。
【参考資料】
第30回海の公園「どんど焼き」を開催します!|横浜市
新宿雀ノ森のお焚き上げ|文化遺産オンライン
手元に残す年賀状・手紙の保管方法は?
住所録として手元に残す年賀状や手紙は、使いやすく効率的に保管したいもの。また、大切な方からの手紙やおしゃれな絵はがきは、劣化しないように大事に扱いたいですよね。
ここからは、年賀状や手紙の保管方法をご紹介します。
一時的な保管はコンパクトに
住所確認のために年賀状や手紙を保管する場合は、コンパクトに収納できて簡単に取り出せることを重視しましょう。例えば、次の方法なら処分するときも粘着テープを巻くだけで個人情報対策ができます。
- 輪ゴムで束ねる
- 袋に入れる
- ダブルクリップで留める
- 100円ショップなどの「はがきケース」に入れる
年賀状や手紙の束をひとまとめにして収納する場合は、紙やマスキングテープで作ったラベルに「いつ届いたものか」「家族の誰に宛てたものか」などをメモしておくとよいでしょう。
頻繁に年賀状で住所を確認している場合は、ただ束ねるよりもクリアファイルポケット付きバインダーに綴じる方が便利です。はがきサイズのファイルボックスやレタースタンドを使って、すぐ手に取れるところに置いておくのもよいでしょう。穴を開けて2穴バインダーに綴じたり、カードリングを通したりするのもおすすめです。
大切な年賀状・手紙は劣化対策もしっかりと
大切にしたい年賀状や手紙は、直射日光や湿気を避け、温度変化の少ない場所に保管しましょう。収納には、酸性紙ではなくアルカリ性の紙で作られたファイルやバインダーを使うと傷みにくいです。
また、額に入れて飾ったり、壁やコルクボードに貼ったりするのもおすすめです。さらに、はがきは厚みがあるため、端をきちっと揃えて一辺に布テープを貼るだけで製本できます。文庫本のような見た目で保管できるため、表紙と背表紙をつけたり、マスキングテープやスタンプで飾ったりして楽しんでみてください。
デジタル化もおすすめ
年賀状や手紙は、スマホカメラやプリンターでスキャンしてデータ化するのもおすすめです。劣化がないうえ、ファイル名をつけて保存すればすぐに検索できます。
近年は、はがきなどの紙物のデジタル化に特化したアプリ・ソフトも多いです。取り込んだ年賀状の写真を補正してくれたり、自動で文字を認識して検索しやすく管理してくれるものもあります。思い出の手紙など、大切なものほど万が一に備えてデータ化しておくとよいでしょう。
まとめ
年賀状や手紙には、名前や住所、相手の家族写真や連絡先まで記載されています。個人情報が他人にわからないように、十分配慮して処分しましょう。
捨てづらい年賀状や手紙は、どんど焼きやお焚き上げで供養してもらうこともできます。また、手元に残すものは保管方法にも工夫してみてください。






















