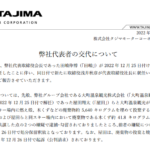ご家庭に溜まりがちな使っていないケーブル。どう処分すればよいのかわからずにタイミングを逃してしまって、「いつのまにかたくさんある!」と驚いたことはありませんか?
また、長い間使わなかったため用途がわからなくなったケーブルもあるかもしれません。何に使うかわからないからこそ、むやみに捨てると後悔しそうで困りますよね。
この記事では、ケーブルの処分方法をリサイクル・廃棄・リユースの3つに分けて解説します。ケーブルの劣化具合をチェックできるポイントや、使い道がわからないケーブルを断捨離する手順もご紹介していますので、ぜひ試してみてください。
目次
家庭で使うケーブルの種類は?
家電やデジタル機器を購入するたびに、お家に増えていくケーブル。今、ご家庭にどのくらい溜まっているか把握できていますか?
お家の中で使用されることが多いケーブルの種類や用途を表にまとめました。下記のほか、製品専用の電源コードや延長コード、電源タップなども不用品が家庭に溜まりやすいです。
| ケーブルの種類 | 役割 | 主に使用する家電・デバイス |
|---|---|---|
| HDMIケーブル | 映像信号・音声信号・操作信号を同時に伝送する | テレビ、ゲーム機、プロジェクターなど |
| LANケーブル | ネットワーク機器を有線接続する | パソコン、ルーター、スイッチなど |
| USBケーブル | コンピューターに周辺機器を接続する | パソコン、キーボード、プリンターなど |
| オーディオケーブル | 音の電気信号を伝送する | アンプ、コンポ、ヘッドホンなど |
| 充電ケーブル | 家電やデバイスを充電する | スマートフォン、モバイルバッテリーなど |
ちなみに、コードとケーブルの違いはその「構造」です。コードは「電線+電気を通さない素材の被膜のみ」で、ケーブルにはその上にカバーが付いています。そのため、ケーブルの方が強度・耐久性ともに高いです。
ケーブルの劣化をチェックする方法
不要なケーブルの処分方法を決める前に、烈火の程度をチェックしてみましょう。接続できる家電につないでみるのが確実ですが、ケーブルの見た目で判断することも可能です。
ケーブルが使えなくなる原因は、多くの場合「接合部分やプラグの付け根の断線」です。プラグやその周辺を観察して以下の項目に当てはまる部分があれば、リサイクルや廃棄で処分しましょう。
- 被覆がひび割れている
- コネクタ部分にひびが入っている
- 銅線が表に出てきている
- ほかの部分と色が違う
- 端子(差し込み部分)がゆがんでいる
また、ケーブルを指で触ってみて、不自然に折れている箇所やくにゃくにゃと柔らかい部分がある場合も断線している可能性が高いです。
断線していないかどうかのチェックをクリアしたケーブルは、ぜひリユースを検討してみてください。
ケーブルの処分方法① 「小型家電リサイクル」の回収に出す
不要なケーブルは、自治体が実施している「小型家電リサイクル」の回収に出して処分するのがおすすめです。
ケーブルをはじめ、普段使っている小型家電には、鉄・アルミ・銅・レアメタルなどの貴重な金属が使用されています。これらの金属は、きちんと回収して処理すればリサイクルできる資源です。せっかく使える資源を、焼却処分や埋め立て処分で失うのはもったいないですよね。
これらの金属を有効活用するために、2013年「小型家電リサイクル法」が施行されました。全国の各自治体では、小型家電リサイクル法に基づいて対象製品を回収しています。
回収された小型家電は、国の認定事業者がきちんとリサイクルしてくれるため信頼性・安全性が保障されています。ケーブルやコードも多くの自治体で回収対象とされているので、ぜひ利用してみてください。
【参考資料】
小型家電リサイクル法とは|一般社団法人 小型家電リサイクル協会
認定事業者とは|一般社団法人 小型家電リサイクル協会
「小型家電回収ボックス」を使うと簡単に処分できる
各自治体では、小型家電リサイクル法に基づいて「小型家電回収ボックス」を設置しています。ケーブルは、この回収ボックスに入れてリサイクルに出すのがおすすめです。
「小型家電回収ボックス」とは、小型家電に使われている金属を再資源化するために各自治体が設置しているボックスです。不要な小型家電を投入するだけで処分できるうえ、費用もかかりません。
また、回収ボックスは各自治体の役場や家電量販店、スーパーマーケットなどに設置されているため、用事のついでに処分できます。自治体ホームページに設置場所が掲載されているので、ぜひチェックしてみてください。
【参考資料】
使用済み小型家電のリサイクル|政府広報オンライン
ケーブルを小型家電回収ボックスに入れる際の注意点
ケーブルを小型家電回収ボックスに入れる際は、次の3点に注意してください。
- 「リサイクル回収ボックス」には入れない
- 回収ボックスの投入口よりも大きい製品は対象外
- ケーブルは結束バンドなどでまとめておく
小型家電回収ボックスが設置されている場所には、似た名称の「リサイクル回収ボックス」が設置されている場合があります。「リサイクル回収ボックス」は、モバイルバッテリーなどの小型充電式電池を回収するためのボックスです。ややこしいですが、間違えてケーブルを入れないように気を付けましょう。
また、小型家電回収ボックスで処分できるのは、投入口に入るサイズの製品に限られています。回収ボックスの投入口は25cm×10cmほどの場合が多いため、長くてボリュームのあるケーブルは入らない可能性もあります。その場合は、次にご紹介する方法も検討してみてください。
小型家電回収ボックスに入らないケーブルは?
自治体によっては、次の方法でも小型家電を回収している場合もあります。
- ステーション回収:ごみ回収場所に「小型家電」という分別枠を設ける
- イベント回収:地域のイベントで回収する
- ピックアップ回収:不燃ごみや粗大ごみと同じように回収した小型家電を処理施設で選り分ける
これらの方法はボックス回収よりもサイズ規定が緩いケースも多いです。お住まいの自治体の実施状況をチェックしてみてください。
また、国の認定事業者に不要なケーブルを送る「宅配回収」も利用可能です。宅配回収では、不用品そのもののサイズではなく梱包する箱の大きさや重量が基準になるため、長いケーブルも問題なく回収してもらえます。
ただし、処分費用は認定事業者によって大きく異なります。「送料無料で回収費が必要」「送料は自己負担で回収費は無し」「特定品目のみ無料で回収」などのバリエーションがあるため、料金形態は事前に確認しておきましょう。
【参考資料】
回収方法|一般社団法人 小型家電リサイクル協会
ケーブルの処分方法② 不燃ごみ・粗大ごみとして廃棄
不要なケーブルは、小型家電のリサイクル回収以外の方法でも処分できます。
先にお伝えしたように、ケーブルに使われている金属は再利用可能な資源です。なるべくリサイクルに回したいものですが、多くの自治体では「不燃ごみ」としても処分できます。ほかの不燃ごみと同じように専用のごみ袋に入れて、指定の回収場所に出すだけでももちろんOKです。
ただし、自治体によっては全長30cm以上のケーブルは「粗大ごみ」として扱う可能性もあります。粗大ごみを捨てるには別途料金がかかるため、事前にお住まいの地域の分別ルールをしっかりと確認しておきましょう。
ケーブルを廃棄する際の注意点
ケーブルを処分する際に気を付けてほしいポイントは次の2つです。ごみ回収に出す場合だけでなく、リサイクル回収に出すときにも十分に注意してください。
- 感電対策は万全に
- ケーブルやコードを切断するのは危険!
具体的な方法を解説します。
発火・感電対策は万全に
不要なケーブルは、回収に出す前に発火・感電対策を施しましょう。
機器に接続していないケーブルに電流は流れていません。しかし、回収ボックスやごみ収集車の内部で何かの拍子に電気が生じる恐れもあります。ふいに発生した電気から火災や感電事故が起こる可能性もないとはいえません。
ケーブルのコネクタや芯線など、金属が表から見えている箇所にはしっかりビニールテープを巻き、絶縁処理を施してください。4回ほどぐるぐると巻きつけるのがおすすめです。断線した銅線が露出している箇所があれば、その部分も保護しましょう。
また、感電防止のため濡れた手でケーブルを扱うのはNGです。使用中でなくても、乾いた手で扱うようにしてください。
【参考資料】
電源コードで火災事故|日本電気協会 関西支部
ケーブルやコードを切断するのは危険!
ケーブルやコードを処分するために切断する必要はありません。
「小型家電回収ボックスに入れたいから」「粗大ごみのサイズだけれど、不燃ごみで出したいから」という場合もあるかもしれませんが、切断する際に怪我をする恐れもあります。太いケーブルを切るには力も必要なため、より危険です。
ケーブルを処分する際は、あくまで「あまり力を加えず自然にまとめ、結束バンドで束ねる」程度に留めましょう。束ねたサイズで処分できない場合は、ほかの方法を検討してみてください。
【参考資料】
電源コード「5.素人修理で発火」|独立行政法人 製品評価技術基盤機構
ケーブルの処分方法③ リユースへ回す
「問題なく使用できるケーブルだけど、不要だから処分したい」
このような場合は、リサイクルや廃棄ではなくリユースがおすすめです。リサイクルショップや中古品買取業者、またはフリマアプリやネットオークションの利用を検討してみてください。
特に、メーカー純正品のケーブルや高級オーディオのケーブルは、多くの業者で買取対象になっています。ケーブルが付属している家電と一緒に持ち込むと、買取金額も上がりやすいです。
しかし、家電付属でもケーブル単体では値段がつきにくい場合があります。また、通電が確認できないケーブルは買い取ってもらえません。フリマアプリやネットオークションに出品して買い手がついても、使えなければ返金対応やトラブルに発展してしまいます。
不要なケーブルを手放したいときは、お手持ちのケーブルが「断線していてもう使えない」のか「問題なく使えるけれども不要」なのかを明確にしたうえで、リサイクル・廃棄に出すかリユースに回すか決めるとよいでしょう。
使い道がわからないケーブルはどうしたらいい?
「これ、どの家電につなぐものだっけ?」と、使い道が分からないケーブルが溜まっているご家庭も多いのではないでしょうか。似たようなケーブルがたくさんあるから断捨離したいけれども、いざ必要になったら困るし…と悩みますよね。
ケーブルの断捨離は、まず使い道をはっきりさせることから始めましょう。次の手順で、お家にあるケーブルをチェックしてみてください。
- 現在家にあるケーブル接続が必要な家電・デバイスをリストアップ
- ケーブルをコネクタの形状ごとにざっくり分類
- リストに挙げた家電やデバイスと照らし合わせる
スマホカメラでケーブルを撮影し、「Googleレンズ」で画像検索するのもおすすめです。
ケーブルの断捨離のコツ
それぞれのケーブルの使い道がわかったら、必要かどうかを判断していきます。
既にケーブルが対応している家電がお家になければ迷わず処分できますが、複数の家電やデバイスで使用できる製品だと迷いますよね。
その場合、手元に残す本数は「使う先の口数+予備」を目安にするのがおすすめです。同じ用途のケーブルやコードは、先にご紹介したポイントをチェックして状態がよいものを残しましょう。
手元に残すケーブルは、マスキングテープで用途をラベリングしておきます。おおまかな種類ごとにラベルの色を変えると一目見ただけでもわかりやすいです。収納する際は、無理のないハリ感でまとめて結束バンドで束ねると、ケーブルの劣化を軽減できます。
まとめ
ケーブルの処分について、リサイクル・廃棄・リユースの3つの方法を解説しました。
ケーブルに使われている金属は、適切に回収・リサイクルすれば再利用できる貴重な資源です。ご家庭の不要なケーブルは、ぜひ「小型家電リサイクル」の回収に出してみてください。簡単に処分できるうえ、環境にも優しいです。
そのほか、もう使えないケーブルは不燃ごみや粗大ごみとして廃棄したり、まだ使用可能であればリサイクルショップやフリマアプリなどで売却したりすることができます。ご自分に無理のない方法で処分しましょう。