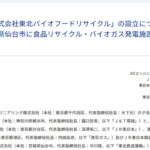今回は産業廃棄物の一種である「木くず」について解説します。
木くずとは?
産業廃棄物の一種である「木くず」とは、建設現場にて発生した木くず、パルプ製造業にて発生した木くず、木材や家具などの木製品を製造するときに発生した木くず、輸入した木材の卸売の際に発生した木くず、事業活動から生じたPCB※が染み込んでいる木くずなどがあります。
また一般廃棄物の扱いとなる木くずとの違いは、多量排出性や有害物質の含有の差異などでわけられます。
※PCBとは
PCBとはポリ塩化ビフェニルのことです。化学的に安定している、燃えにくい、絶縁性が高いという理由で電気機器の絶縁油、感圧複写紙や熱交換器の熱媒体などに幅広く利用されていましたが、PCBの含まれた廃棄物は簡単には分解できず、発がん性などの人の健康および生活環境に被害を生ずるおそれから、昭和47年にはPCBの製造が禁止されました。
木くずの種類
木くずには産業廃棄物として扱われるものと、一般廃棄物として扱われるものがあります。
| 産業廃棄物 |
|
|---|---|
| 一般廃棄物 |
|
木くずの廃棄量統計
平成28年度の種類別排出量の統計によると、汚泥が約167,316千トン(全体の43.2%)、動物のふん尿が約80,465千トン(20.8%)、がれき類が約63,587千トン(16.4%)という順番になっており、この3種類が全体の約8割を占めています。
木くずは 7,098千トン(1.8%)となっており、平成27年度は7,248千トン(1.9%)であったため、前年度と比べ0.1%減少しています。
参照環境省 産業廃棄物の排出及び処理状況等(平成28年度実績)について
木くずのリサイクル
産業廃棄物である木くずの処理方法は、チップ化、直接埋立・単純焼却、燃料化、エネルギー回収も含む焼却、堆肥化などがあります。
廃棄物を再利用していくために平成12年5月に建設リサイクル法が制定されました。建設リサイクル法では、特定建設資材(プレキャスト板などを含むコンクリート、アスファルト・コンクリート、木材)を使った一定規模以上の建築物の解体工事や新築工事の受注者などに対し、分別解体や再資源化などを行うように義務付けています。これによって、建設時に発生した木くずは、木材チップなどに再資源化されます。
木くずを処分する際の課題

木くずには一般廃棄物と産業廃棄物がありますが、その区分について一般廃棄物として扱われる流木の処理問題があります。なぜなら、流木は塩分を含むことや、洪水などの自然災害にて発生した場合に木の量や質が様々で、各施設での処理に時間と費用がかかり大きな負担となっています。
また、大型の流木が一般廃棄物であるのにも関わらず、公共施設の搬入規制により、通常の一般廃棄物のように処理できないことも課題の一つです。流木は一度に大量発生し処理に時間がかかった場合、腐食による臭いの問題が発生します。流木アートやDIYインテリアの材料として近年注目されている身近な存在の流木ですが、処理工程を細かく見ていくと産業廃棄物処理にも大きく関わってきます。
まとめ
建設リサイクル法によって、産業廃棄物の木くずの再資源化がすすめられている一方で、一般廃棄物として扱われている大きな木くずや大量の木くず処理にはまだ課題があります。
建設現場で木くずや様々な大量の産業廃棄物が出た場合、大型の粉砕機や自走式スクリーン機の投入により、処理する時間や人員などのコスト削減につながっています。機材の入手方法も新規購入だけでなく、レンタルもできるようになりました。こうした大量の廃棄物処理への課題解消にむけて、レンタル機材の投入は今後活躍の場が広がると思われます。