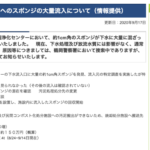建設現場で出る土砂は、処理方法を誤ると法令違反や高コストなってしまう場合があるのはご存じですか?
リサイクル法では「対象外」でも、土砂には実務上の対応が必要です。
現場での再利用や処分コストの削減が求められる中、「ふるい機」が注目されています。
本記事では、土砂の法令的な位置づけから、実務・コスト・再利用までを詳しく解説していきます。
目次
建設リサイクル法とは?土砂の扱いに注意
建設リサイクル法は、建設工事に伴って発生する資材の再資源化と適正処理を目的とした法律です。
コンクリートやアスファルト、木材などの特定建設資材が対象となりますが、土砂は原則としてこの法律の対象外とされています。
参考:環境省「建設リサイクル法の概要」
ただし対象外であっても、土砂の処理を誤ると不法投棄と見なされる可能性があります。
まずは、建設リサイクル法の基本と、土砂を扱う上での注意点について解説します。
建設リサイクル法の対象は「特定建設資材」
建設リサイクル法の対象となるのは、「特定建設資材」と呼ばれる資材です。
「特定建設資材(とくていけんせつしざい)」とは建設リサイクル法という法律で「リサイクルをしなければいけない」と決められている建設材料のことです。
具体的には、コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材などで、これらが一定量以上発生する建設工事を行う場合には、分別解体と再資源化が義務付けられます。
たとえば、解体工事や新築工事、修繕・模様替え工事などが該当します。
これにより、廃棄物の減量とリサイクルの促進が図られています。
土砂は原則として対象外。しかし注意が必要
一方で、建設工事で発生する「土砂」は、建設リサイクル法の対象には含まれていません。
土砂は自然由来のものとされ、「建設副産物」としての扱いになります。
しかし、処理方法によっては、産業廃棄物とみなされる場合があるため注意が必要です。
たとえば、がれきや廃材などが混ざったままの状態で放置・処分した場合、法令違反となるおそれがあります。
土砂の性状や混入物の有無に応じた適切な対応が求められます。
土砂の処理にもルールがある
たとえ建設リサイクル法の対象外であっても、土砂の処理には責任が伴います。
無許可の土地への搬入や処分は、不法投棄として行政処分や罰則の対象となります。
そのため、残土処理を行う際は、運搬先の許可状況の確認や、契約書類の整備、搬出記録の保存などが重要です。
また再利用を前提とした選別やふるい分けによって、処分コストを削減できる可能性もあります。
法令を順守しつつ、経済的にも合理的な処理を行うことが、現場管理者には求められます。
建設現場で出る土砂の処理方法は?
建設現場で大量に発生する「土砂」は、法的には建設リサイクル法の対象外ですが、実務上は処理方法に細心の注意が必要です。
性質や混入物の有無によって分類が異なり、それに応じて処理ルートも大きく変わります。
ここからは、現場で発生する土砂の分類と、それぞれに適した処理方法について整理します。
土砂には複数の呼び方と区分がある
建設現場で出る「土砂」は、ひとくくりにされがちですが、実際にはいくつかの種類に分けられます。
代表的なのが以下の3つです。
- 建設発生土(残土)
掘削などによって発生した自然由来の土。通常は再利用の対象。 - 混合残土・汚泥
コンクリート片やゴミ、植物根などが混入しているもの。選別や処理が必要。 - 産業廃棄物としての土砂
混入物や性状によって廃棄物と判断される場合、廃掃法に基づく対応が必要になる。
これらを正しく見分けることで、処理コスト・手間・法令対応が大きく変わってきます。
処理ルートは「再利用」「搬出」「処分」の3択
土砂の扱い方としては、主に次の3パターンがあります。
- 現場内での再利用(埋戻し、整地材など)
コスト削減の最善策。性状が良好な場合に限る。 - 搬出処分(処分場への持ち込み)
再利用できない場合、許可業者による運搬・処理が必要。 - リサイクル施設での処理後再利用
ふるい機などで選別・分別し、資材化する方法。再利用と処分の中間的な選択肢。
重要なのは、「土砂の状態を見極めて、最適な処理ルートを選ぶ」ことです。
曖昧な判断がトラブルを生む
「これは残土でいいはず」と安易に判断してしまうと、以下のようなトラブルにつながる恐れがあります。
- 実は混入物が多くて処分場に断られた
- 再利用した埋戻し土が不適格で手戻りが発生
- 産業廃棄物に該当するのに契約・マニフェストなしで処理していた
とくに下請け業者が搬出を担当している場合、法令意識のギャップから元請けが巻き込まれるケースも少なくありません。
現場で発生した土砂の性状確認や分別処理の体制を整えることで、処理コストを大きく抑えられるだけでなく、元請け・施主からの信頼維持にもつながります。
再利用できる土砂を的確に見極め、適切に処理・記録することが、これからの現場管理には不可欠です。
土砂処理のコストと現場課題
建設現場で土砂を処理する際、「とにかく処分すればいい」と考えていませんか?
実はこの考え方が、予想外のコスト増やトラブルの原因になっています。
土砂の性状や混入物の確認を怠ったり、分別せずに一括処理したりすると、処分費だけでなく運搬費や手戻りのリスクも跳ね上がります。
ここからは、現場で起きがちな課題と、その背景にあるコスト構造について解説していきます。
土砂の処分費は想像以上に高い
まず押さえておきたいのが、処分費用の高騰です。
ひと昔前まで、残土処分は比較的安価に済んでいました。
しかし現在では、以下の理由により処分費が上昇しています。
- 最終処分場の受け入れ制限(埋立容量の減少)
- 土砂に混入する異物の確認強化
- 運搬業者の人件費・燃料費の高騰
さらに、性状が悪い土砂(ガラやごみ混入など)は受け入れ拒否されるケースもあり、その場で再積込・再処理が必要になることもあります。
結果として、「予定の倍以上のコストがかかった」という現場は珍しくありません。
「土砂=処分」だけでは非効率
再利用可能な土砂まで、まとめて処分していませんか?
現場でふるい分けや選別を行い、「使える土」と「使えない土」を分けておけば、再利用によって大幅なコスト削減が可能です。
たとえば、土砂を処分する場合は処分費以外にも運搬費などがかかります。
しかし場内再利用をすれば、コストはほぼかかりません。
分けるだけで大幅にコストが変わってきます。
土砂処理は、ただの作業ではなく「コストマネジメント」です。
法令違反を防ぐだけでなく、現場の経費・段取り・再利用効率にまで影響を与えます。
つまり、土砂をどう扱うかで、現場の品質や評価も左右されるということです。
現場対応がコストを左右する3つの落とし穴
以下のような対応ミスは、現場における典型的な“ムダ”につながります。
- 混合土をそのまま処分してしまう
使える土まで高い費用をかけて処分している - 埋戻しに使った土の性状が悪く、再施工が発生
重機・人件費が二重にかかる - 処分先で受け入れ拒否され、再搬出が必要に
運搬費+時間のロス
これらを防ぐには、事前の選別・ふるい分けが重要です。
とくに混入物が多い土砂には、ふるい機を用いた現場選別が有効です。
土砂の再利用とふるい機という選択肢

建設現場で発生した土砂は、適切に処理しないと処分費がかさむだけでなく、工事の進行にも影響します。
しかし一方で、「ふるい分け」を行えば、再利用できる土砂も多く、コストを大きく下げることができます。
現場のムダを減らし、作業効率と経済性を両立させるために、いま注目されているのがふるい機です。
土砂を再利用できれば、処分費が大幅ダウン
土砂を再利用できれば、搬出・処分費はもちろん、搬入する埋戻し材や路盤材の購入費も不要になります。
例えば、ふるい分けで石やガラを除去した土は、以下のような場面で有効に活用できます。
- 基礎埋戻し
- 仮設道路の整地材
- 盛土の充填材
- 法面の補修土
こうした再利用は、処分費を最大で30〜50%削減できる可能性があります。
コストだけでなく、運搬回数も減らせるため、作業全体の効率アップにもつながります。
再利用を阻む「混合土」問題
ただし、現実には「そのままでは使えない土」も多く存在します。
具体的には、以下のような混入物があると、再利用は難しくなります。
- コンクリートガラや鉄くず
- 植物の根や枯草
- 生活ごみや産廃
- 水分が多すぎる泥状土
これらの異物が混ざっていると、埋戻し材に適さず、再利用どころか処分費が割増になるケースもあります。
この問題を解決するために、有効なのが「ふるい機」を使った現場選別です。
ふるい機で「使える土砂」に変える
ふるい機とは、土砂を振動や回転でふるい分け、粒径ごとに分類・異物除去するための装置です。
これにより、ガラ・ゴミ・根などを簡単に分離でき、再利用に適した状態の土砂を確保できます。
ふるい機の活用により、以下のような現場メリットが得られます。
- 再利用率の向上(混合土→資材土へ)
- 運搬・処分費の大幅削減
- 現場に応じた分級調整が可能
- 作業員による手選別の手間を削減
特に現場スペースが限られる都市部や、処分費が高騰している地域では、ふるい機の導入で現場負担が劇的に軽減されるケースもあります。
ある中規模造成現場(500m³の残土発生)では、ふるい機を活用し、以下のようなコスト削減効果がありました。
- 約70%の土砂を再利用(埋戻しに転用)
- 搬出量を150m³に抑制
結果として、処分費と運搬費を合わせて約80万円削減しました。
ふるい作業自体は2日間で完了し、作業効率にも影響なし。
「ふるいさえ入れておけば処分量は抑えられる」と、以後の現場にも導入されるようになったそうです。
ふるい機の導入は、単なる機材選定ではありません。
「資源を捨てずに活かす」ことで、現場の利益と環境対応を同時に実現する手段なのです。
ふるい機の導入方法は?
「ふるい機が現場で役立つのは分かった。でも導入するには高いんじゃないか…?」
そう感じた方も多いかもしれません。
実際、ふるい機の購入には数百万円単位の費用がかかることもあります。
しかし、いま主流なのは“レンタル活用”という選択肢です。
現場の規模や用途に合わせて、最小限のコストで導入できる方法として、多くの建設現場で選ばれています。
購入ではなくレンタルという選択肢
ふるい機を購入する場合、サイズや能力によりますが、300万〜800万円が相場です。
購入には以下のような費用と手間が発生します。
- 購入費(初期コスト)
- 設置スペース・保管場所の確保
- オペレーターへの教育や操作マニュアルの整備
- メンテナンスや故障時の修理費
特に「毎回の現場で必ず使うとは限らない」という事業者にとって、購入はコストリスクになりやすいのが実情です。
ふるい機レンタルを活用すれば、必要な期間・台数だけを柔軟に導入できます。
そのメリットは明確です。
- 短期レンタルで導入コストを大幅カット
- 設置・撤去サポート込みで運用もスムーズ
- 故障時は交換対応や保守付きで安心
- 現場に合ったタイプを都度選べる(回転式、バイブ式など)
たとえば、「3日だけ使いたい」「今の現場は狭いのでコンパクトな機種がいい」など、現場事情に応じた使い方が可能です。
ふるい機レンタルの流れ
ふるい機レンタルの流れは次の通りです。
- 現場内容や土質をヒアリング
- 機種の選定・見積もり
- 搬入・設置(オペレーション説明あり)
- 使用終了後の撤去・引き取り
通常は電話やフォームで相談〜数日で手配完了できるため、急な現場変更にも対応しやすいのが強みです。
現場の利益率を高めるには、コストを抑えるだけでなく、必要なときに必要な機材を使える柔軟性が重要です。
ふるい機レンタルなら、導入のハードルを大きく下げながら、資材の再利用と処理効率を最大化できます。
現場対応チェックリスト
「ふるい機を使えば再利用できる」と言っても、すべての土砂が再利用できるわけではありません。
再利用が可能かどうかを見極めるための現場判断が重要です。
ここでは、再利用の可否を判断するためのチェックポイントと、判断ミスを防ぐための実践的なコツをご紹介します。
再利用できる土砂の特徴とは?
再利用に適した土砂には、以下のような特徴があります。
- 粒径が一定(極端な大粒・極小粒がない)
- 有機物(木くず・根など)が含まれていない
- 建設廃材(コンクリートガラ、プラスチックなど)が混入していない
- 適度な含水率(水分が多すぎない)
- 臭気や油分などの異常がない
これらを満たしていれば、埋戻しや仮設道路への再利用が可能な場合が多いです。
再利用の際には、必ず再利用可能か確認してから使用してください。
再利用の判断に迷う場合は、「どこで使うか」を軸に考えるとスムーズです。
たとえば、重要構造物の下部に使う埋戻し材は厳しく評価する必要がありますが、仮設道路や仮置き場などであれば、多少の粒度のばらつきがあっても問題にならないケースもあります。
現場で使える再利用判断チェックリスト
以下のチェック項目を現場で活用すれば、土砂の状態を簡易に評価できます。
- 見た目に混入物がないか確認した
- 異臭・油分・液状化の兆候がない
- 手で握って崩れる程度の含水率
- ふるい機での分別処理を行った or 行う予定がある
- 再利用目的が明確になっている(例:基礎埋戻し・盛土など)
これらの項目を満たせば、再利用の方向で検討してよいといえるでしょう。
現場ごとに判断基準がバラバラだと、手戻りや無駄な処分が発生します。
だからこそ、チェックリストと処理フローを整備し、再利用の判断を標準化することが、現場の生産性と信頼性を高める鍵になります。
建設現場のコストと法令を両立させるふるい機を

建設リサイクル法の対象には含まれない「土砂」ですが、現場での扱い方ひとつで処分コスト・再利用率・施主からの信頼に大きな差が出ます。
土砂の分別や性状確認を後回しにすれば、ムダな費用やトラブルにつながる可能性もあります。
だからこそ、ふるい機などの選別機を導入して、使える土と捨てる土を明確に分けることが、現場経営において大きな価値を持つのです。
ふるい機は単なる機械ではなく、「現場全体のムダを減らすパートナー」ともいえる存在です。
とくにレンタルであれば、必要なときだけ手軽に使えるため、初めての導入でもリスクは低く、効果は即日実感できます。
新西工業株式会社では、ふるい機のレンタルサービスをおこなっています。
無駄な処分費を減らしたい
再利用できる土を無駄にしたくない
法令も守りながらコストも抑えたい
上記のようなお悩みがある方、是非1度ふるい機のレンタル活用を検討してみてください。