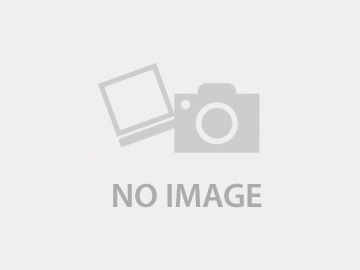「電子マニフェストの導入方法を知りたい」
「産廃マニフェストを電子化したいが、難しそう」
このようなお悩みはありませんか?
本記事では、産廃マニフェストの電子化について解説していきます。
紙マニフェストとの違いや具体的な導入方法などを知り、自社のマニフェスト管理の参考にしてください。
目次
産廃マニフェストとは
産廃マニフェストとは、産業廃棄物の「排出から最終処分まで」の流れを記録・追跡するための管理票です。
正式名称は「産業廃棄物管理票」といいます。
産業廃棄物が適切に処理されたかどうかを把握・管理し、不法投棄などが起こらないように排出事業者が処理業者や運搬業者に交付する義務があります。
産廃マニフェストを交付していない場合、 廃棄物処理法違反となり、行政指導や罰則の対象になります。
特に、以下の場合は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
- マニフェストを交付しなかった
- 虚偽の内容を記載した
- 保存期間(5年間)を守らなかった
産廃マニフェストは、排出事業者が産業廃棄物を適正に処理したことを示す重要な証拠です。
たとえば処理業者側で不適正な処理が行われた場合でも、マニフェストをきちんと交付・保管していれば、排出事業者が法令に沿って行動したことを証明できます。
産廃マニフェストは自社を守ってくれる証拠にもなるのです。
(参考:環境省「産業廃棄物管理票・電子マニフェスト関連」)
紙マニフェストと電子マニフェストの違い
紙マニフェストと電子マニフェストは、報告する内容に違いはありませんが、その他の部分で大きな違いがあります。
以下の表にまとめました。
| 項目 | 紙マニフェスト | 電子マニフェスト |
| 形式 | 複写式の用紙でやりとり | インターネット上の専用サイト(JWNET)に入力・共有 |
| 交付方法 | 手書きまたは印刷して手渡し | サイトにログインしてデータ入力・送信 |
| 確認方法 | 手元の控えと返送を照合 | サイト上でリアルタイムに確認 |
| 保存期間 | 5年間の保管義務 | サイト上に自動保存 |
| 報告書制作 | 手作業で集計・記載 | 自動集計で簡単作業 |
| ミスや記載漏れ | 手書きのため注意が必要 | 入力項目があるため、記載漏れは防げる |
| 導入コスト | 用紙と郵便代のみ | インターネット環境を整える初期費用、サイトの利用料がかかる |
| 導入のしやすさ | 手軽に導入できる | 初期費用・初期設定が必要 |
JWNETは公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が運営する電子マニフェストシステムで、産業廃棄物の収集運搬や処分に関する情報を電子的に管理・報告するための仕組みです。
従来は紙マニフェストが主流で、すべて手作業でおこなわれていました。
しかし電子マニフェストが普及してからは、効率の良さや便利さから電子化が推進されています。
電子マニフェストの義務化
2020年4月より以下の条件を満たす事業者は特別管理、産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の処理を委託する際、電子マニフェストの使用が義務付けられました。
・前々年度において、特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の年間発生量が50トン以上の事業場を有する事業者
廃棄物の適正処理を確保し、不法投棄などの問題を防止するために導入されました。
義務対象事業者が電子マニフェストを使用しない場合、以下のような行政措置が取られる可能性があります。
- 改善勧告
- 事業者名の公表
- 措置命令
措置命令に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることがあります。
しかし、例外もあります。
- 電子マニフェストシステムへのアクセスが困難な場合(例:通信障害、災害時)
- 電子マニフェストに対応した処理業者が存在しない地域での排出
上記の場合、紙マニフェストの使用が認められる可能性があります。
その際、紙マニフェストの備考欄に必ず理由を明記しましょう。
(参考:環境省「Q&A 電子マニフェスト使用の一部義務化等について」)
電子マニフェストのメリットとデメリット
ここからは電子マニフェストのメリットデメリットについて解説していきます。
電子マニフェストのメリット5選
まずは、電子マニフェスト導入のメリットをご紹介します。
ミス防止
紙マニフェストではすべて手作業で作成するため、間違いやミスが起きやすいです。
一方電子マニフェストにはあらかじめ入力項目があり、入力漏れがあると登録や報告が出来ない仕様になっています。
そのため記入漏れを防げます。
また終了報告の期限が近付くとお知らせしてくれるので、報告忘れも防止できます。
処理状況をリアルタイムで確認
紙マニフェストの場合、手作業で記入し用紙を手渡していくため、処理が完了してマニフェストが戻ってくるまで、処理状況の把握ができませんでした。
しかし電子マニフェストは排出事業者・運搬業者・処分業者が記入・閲覧できるため、現在の処理状況をリアルタイムで確認できます。
また三者の目があるため、不適切なマニフェストの登録も防げます。
マニフェストの保管が不要
先ほども記載した通り、紙マニフェストには5年間の保管義務があり、破ると罰則や行政指導が入る場合があります。
しかし電子マニフェストは情報処理センターが管理するため、保管の必要がありません。
大切な書類を失くしてしまう心配がなく、保管スペースも不要です。
交付状況の報告が不要
紙マニフェストでは、排出事業者に対して毎年1年間分のマニフェスト交付等の報告が義務付けられています。
手作業で集計しまとめるため、時間と手間がかかります。
しかし電子マニフェストは、情報処理センターがまとめて報告してくれます。
そのため、集計や報告作業をする必要がありません。
事務処理の効率化
紙マニフェストでは、マニフェストの記入から渡す作業まで、すべて人の手でおこなわれていました。
しかし電子マニフェストはそれぞれの業者がサイトに記入するため、人員削減や効率化につながっています。
電子マニフェストのデメリット3選
ここからは電子マニフェストのデメリットをご紹介します。
コストがかかる
電子マニフェスト導入の際はインターネット環境の準備やサイトの利用に費用がかかります。
特に排出事業者は、産業廃棄物の排出量が多ければサイト利用費も上がります。
一方紙マニフェストは、紙代と郵送代のみのため、コストは抑えられます。
関係する全事業者が電子マニフェストに加入が必要
電子マニフェストのルールとして、関係する全事業者が電子マニフェストに加入しなければなりません。
そのため運搬業者や処理業者を選ぶ際、電子マニフェストに対応しているか確認する必要があります。
紙マニフェストは特に確認の必要がありません。
システム障害が起こる可能性
インターネットにはシステム障害が起こる可能性があります。
基本的に、1度報告してしまった電子マニフェストを紙マニフェストで再報告することはできません。
そのためシステムの復旧作業をおこなわなければなりません。
過去には報告期間を延長してもらえた場合もあるようなので、緊急時のマニュアルを作成し、把握しておくと良いでしょう。
紙マニフェストと電子マニフェストはどう選ぶのが良いのか?
紙マニフェストと電子マニフェストのどちらが良いかは一概には言えません。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、排出事業者の業務量や処理件数に応じて使い分けることが大切です。
たとえば、年間を通して産業廃棄物の排出量や排出回数が少ない小規模な事業者であれば、紙マニフェストのほうが導入のハードルが低く、費用も抑えられます。
以下のようなケースは紙マニフェストが向いています。
- 年に数回しか廃棄物が出ない個人事業主の工場
- 排出現場が1か所しかない中小の建設会社
- 排出内容がシンプルで種類が少ない場合
紙マニフェストは、すぐに始められる手軽さが魅力ですが、その一方で、手書きや押印、控えの保存、運搬業者への手渡しなど、1件ごとの作業に手間と時間がかかるというデメリットもあります。
また5年間の保存義務や集計・報告作業も手作業になるため、件数が増えるほど管理が煩雑になります。
一方で排出量や排出回数が多い事業者には、電子マニフェストの導入がおすすめです。
たとえば、以下のような企業は電子マニフェストが向いています。
- 複数の現場を同時に抱えるゼネコンや製造工場
- 排出件数が月に何十件もあるリサイクル業者
- 社内で法令遵守や業務効率を重視したい企業
電子マニフェストは、JWNETのシステムを使ってネット上で情報のやり取りと保存ができるため、入力ミスの防止や進捗確認もリアルタイムで可能です。
報告書も自動集計できるので、事務作業の負担を大幅に軽減できます。
ただし、電子マニフェストの利用には年会費が発生するため、排出件数が少ないとコストパフォーマンスが悪く感じられるかもしれません。
短期的にはコストが気になる電子マニフェストですが、業務効率・法令対応・情報管理のしやすさを考えると、長期的に考えて電子マニフェストの導入をおすすめします。
「処理のたびに紙でやりとりするのが面倒」「報告作業に時間がかかる」と感じている場合は、今こそ電子マニフェストへの切り替えを検討するタイミングかもしれません。
電子マニフェストを導入するための6ステップ
ここからは、電子マニフェストの導入準備から利用開始までを6つのステップに分けて解説していきます。
導入準備から利用開始までの流れを知り、実際に導入する際の参考にしてください。
インターネットに接続できるパソコンを用意する
電子マニフェストを導入するために、まずインターネットに接続できる環境を整えることが第一歩です。
電子マニフェストの運用は、JWNETが提供する専用システムを通じておこなわれるため、常時インターネットに接続できるパソコンが必須となります。
基本的には一般的な業務用パソコンで問題ありませんが、セキュリティソフトやブラウザのバージョンが古いと、正しく表示されない場合があるため注意が必要です。
「現場事務所にはインターネットがない」という場合は、Wi-Fiルーターやモバイル回線を活用して通信環境を整えることも検討しましょう。
スムーズな運用のためには、安定したネット環境と、最低限のPC操作ができるスタッフの配置も重要です。
運搬業者、処分業者が電子マニフェストに対応しているか確認する
電子マニフェストを導入するには、排出事業者だけでなく、運搬業者や処分業者もJWNETに加入している必要があります。
これは、システム上で情報をやり取りするために必要な条件です。
そのため、まずは取引している業者が電子マニフェストに対応しているかを事前に確認することが大切です。
確認方法としては、JWセンター(正式名称:日本産業廃棄物処理振興センター)の公式サイトで、加入している業者の一覧を検索できます。
「業者名」や「地域」などを入力すれば、加入状況を調べることができます。
ただし業者によっては情報を非公開にしている場合もあるため、サイトで見つからないこともあります。
その場合は直接その業者に連絡し、「電子マニフェストに対応していますか?」と確認してみましょう。
もし運搬業者や処分業者が未加入だった場合は、加入をお願いするか、すでに対応している別の業者への切り替えを検討する必要があります。
JWNETへの加入手続きをおこなう
インターネット環境の準備や各業者への確認が完了したら、JWNETへの加入手続きをおこないましょう。
公式サイトから加入することができ、通常は登録した日から利用できます。
電子マニフェストの運用ルールを決める
電子マニフェストは複数人が関わるため、あらかじめ社内や各業者と運用ルールを決めましょう。
具体的には以下の項目についてルールを決めておくとスムーズです。
- マニフェストへの入力場所
- 入力期間
- 入力担当者
- 最終確認のタイミングと担当者
マニフェストの入力場所については、建設現場ではなく、事務所などで代理入力してもらうことも可能です。
その場合は、伝達ミスがないように注意してください。
ルールを明確にし、スムーズにマニフェストを運用していってください。
担当者への説明会をおこなう
電子マニフェストを初めて導入する場合、「どうやって使えばいいの?」「どんなメリットがあるの?」といった疑問や不安を抱えている担当者も少なくありません。
そのため、実際に電子マニフェストの運用に関わる担当者や関係部署のスタッフに向けて、使い方や仕組みを説明する場を設けることが大切です。
説明会では、以下のような内容を共有するとスムーズです。
- 電子マニフェストの基本的な流れ
- JWNETへのログイン方法や操作手順
- 紙マニフェストとの違い
- 電子化によるメリットと注意点
- 実際の運用スケジュールや社内ルール
あらかじめ全体の流れを把握しておくことで、導入後の混乱やミスを防ぎ、スムーズな運用につながります。
導入開始・導入後のサポートをする
電子マニフェストの導入をスタートしたからといって、それで終わりではありません。
本当の運用は、導入後からが始まりです。
特に導入直後は、操作ミスや手続きの漏れなど、慣れない作業によるトラブルが起きやすいタイミングです。
たとえば、登録内容の誤りや、処理業者との連携ミスが発生することもあります。
そうしたリスクを最小限に抑えるためには、社内でいつでも相談やサポートが受けられる体制を整えておくことが重要です。
電子マニフェストの導入で効率化
電子マニフェストの導入には、インターネット環境の整備や関係業者との調整、社内でのルールづくりなど、最初にやるべきことがいくつかあります。
一見ハードルが高そうに感じるかもしれませんが、一度仕組みを整えてしまえば、日々の業務が格段に効率化され、書類の管理や報告作業もスムーズになります。
また法令遵守の強化や情報の透明化といった面でも、電子マニフェストは今後ますます重要になるでしょう。
排出量が多い企業や、複数の現場を抱える事業者にとっては特に大きなメリットがあります。
この機会に電子マニフェストへの移行を検討してみてはいかがでしょうか?
ちなみにわが社では自走式スクリーンのレンタル・販売を手がけており、現場で発生する建設系廃棄物の分別や処理の効率化にも貢献しています。
電子マニフェストの導入とあわせて、現場全体のスマート化を進めていくことをおすすめします。