
建設現場では、残土や廃材の処理が重要な課題となっています。
特に再利用や分別が求められる中、自走式スクリーンの導入が注目されています。
しかし「どの種類を選べば良いのか分からない」という現場の声も少なくありません。
適切な機種を選ぶことは、作業効率の向上やコスト削減につながる重要なポイントです。
この記事では、自走式スクリーンの種類や特徴をご紹介します。
スクリーンの種類や、現場ごとの最適な選び方を知り、スクリーン導入の参考にしてください。
目次
スクリーンとは?

スクリーンは、建設現場などで土砂や廃材をふるい分けるために使用される機械です。
ふるい分けを効率的に行えば、再利用可能な資源を確保でき、処理コストの削減も期待できます。
なかでも自走式スクリーンは、移動が容易な可動式で、さまざまな現場に柔軟に対応できます。
据置式(すえおきしき)とは異なり、設置場所を変えても即座に稼働できるため、省人化や作業時間の短縮にも有効です。
このように、自走式スクリーンは生産性の向上と環境負荷の軽減を同時に実現する重要な設備といえるでしょう。
自走式スクリーンの種類は大きく2つに分かれる
自走式スクリーンには、大きく分けて「振動式」と「回転式」の2種類があります。
振動式はふるい面を振動させて分別する仕組みで、目詰まりしにくく粘性土にも対応しやすい点が特長です。
一方、回転式は円筒やローラーを回転させる構造で、一定の処理能力を安定して発揮しやすいという強みがあります。
それぞれの方式には適した現場条件やふるい分け精度があるため、用途や土質に応じて使い分けることが重要です。
これら2種類の基本的な特徴と違いを整理したうえで、次章以降でタイプ別に詳しくご紹介していきます。
振動式スクリーンの3タイプ
振動式スクリーンは、ふるい面を振動させて土砂や廃材を分別する方式です。
構造がシンプルで、目詰まりしにくいという利点があり、多くの現場で使われています。
中でも代表的なタイプは「グリズリー」「フィンガー」「メッシュ」の3種類です。
それぞれ得意とする分野や対象となる素材が異なるため、現場の条件に応じた選定が欠かせません。
以下では、3タイプの特徴と向いている用途について順番に解説していきます。
グリズリータイプ

グリズリータイプは、粗選別に強いスクリーンです。
太い鉄棒のような構造で構成されたふるい面を持ち、主に大きな岩やガラを取り除くのに適しています。
重機で投入された混合物から、不要な粗大物を最初に分別できるため、後工程の効率も高まります。
特に、解体現場や山間部の造成工事など、大きな異物の混入が多い現場で重宝されています。
粗選別の役割を担うこのタイプは、ほかのスクリーンと組み合わせることで、より効果的な分別が可能です。
フィンガータイプ

フィンガータイプは、粘土質や湿った土に対応しているスクリーンです。
弾力性のあるバー状の構造で、振動によって土砂を分けます。
粘り気のある素材や湿った土が詰まりにくく、メンテナンスの手間も軽減できるという特徴があります。
ぬかるんだ現場や雨天後の作業でも安定して稼働するため、天候の影響を受けやすい工区で活用されています。
ふるい面に柔軟性があるため、土の状態に関係なく安定した処理を行いたい現場に向いています。
メッシュタイプ

メッシュタイプは、細かい粒の選別に最適なスクリーンです。
金属や樹脂製の網目を使ってふるい分けを行います。
細かい土砂や粒状の素材を高精度で分別できるため、再利用目的の素材処理に多く使われています。
粒度の違いによって網の目を変更できるため、必要なふるい分け基準に柔軟に対応できます。
造成地の整地や埋戻し材の調整など、精度が求められる現場で効果を発揮するタイプです。
回転式スクリーンの3タイプ
回転式スクリーンは、ふるい部分を回転させて素材を分別する仕組みの機械です。
安定した処理能力と高い連続稼働性能を備えており、特に大量処理が求められる現場で活用されています。
代表的なタイプは「ディスク」「トロンメル」「ロータリー」の3種類です。
それぞれ構造が異なり、対象とする素材や用途も変わるため、現場のニーズに合った選定が欠かせません。
以下では、各タイプの仕組みと特長、適した利用シーンについて詳しく説明していきます。
ディスクタイプ
ディスクタイプは、粗選別と異物除去に強いスクリーンです。
複数の円盤が回転しながら素材を搬送・分別する構造です。
固形物や異物を取り除きやすく、粗選別に適しているため、建設現場に限らず産業廃棄物処理の分野でも利用されています。
特に木くずや金属片などが混在する混合廃材の処理に強く、異物除去を効率的に行える点が特長です。
粗大ごみや解体廃材を選別したい場合に向いているタイプといえます。
トロンメルタイプ

トロンメルタイプは、建設残土の分別に広く対応しているスクリーンです。
筒状のふるい(ドラム)が回転し、素材を回しながらふるい分ける方式です。
素材が回転と傾斜の力で自然に移動するため、処理が安定しており、多種多様な土砂に対応できます。
粘性土から乾いた砕石まで幅広い素材に使えるため、造成工事や伐採地など多用途の現場で採用されています。
建設残土の再資源化や一次処理に適している、汎用性の高いタイプです。
ロータリータイプは粘性の高い素材にも対応可能
ロータリータイプは、粘性の高い素材にも対応可能なスクリーンです。
複数のローラーとシリンダーが回転しながら素材を分別する構造です。
構造上、粘性のある土や濡れた素材でも詰まりにくく、安定した処理が可能となっています。
コンポストや有機廃棄物、建設副産物の中間処理などにも対応でき、処理対象が難しい現場でも力を発揮します。
他のタイプでは処理が難しい素材を扱いたい現場に最適な選択肢です。
国内製と海外製の違い
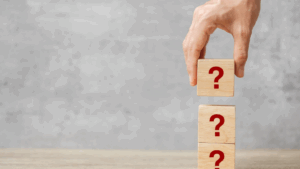
自走式スクリーンを選ぶ際には、機械の種類だけでなく「国内製」か「海外製」かも重要な判断ポイントになります。
国内製と海外製では、サポート体制や設計思想が異なります。
国内製の製品は、日本の土質や現場環境に合わせて作られており、丈夫で壊れにくい設計が特徴です。
さらに、部品の入手や修理対応が早く、アフターサポートも充実しているため、安心して運用できます。
一方、海外製は機能面で先進的なものが多いです。
費用面でも比較的手頃なため、初期費用を抑えたい現場にとっては選びやすい選択肢となります。
しかし、部品供給に時間がかかるケースも見られます。
導入時は性能だけでなく、購入後のサポート体制まで含めて比較検討することが大切です。
自走式スクリーンを選ぶ際の3つのポイント

自走式スクリーンを導入する際は、「どの機種を選ぶか」が作業効率やコストに大きく関わります。
現場の用途や土質、処理量などを考慮しないと、期待した性能を発揮できないこともあります。
そのため、使用目的や素材の種類、日々の運用条件に合わせた選定が欠かせません。
ここからは、自走式スクリーンの選び方のポイントを3つの視点から解説します。
用途に応じて選ぶことが失敗を防ぐ第一歩
自走式スクリーンは、現場の目的に合ったタイプを選ぶことが基本です。
例えば、造成工事や解体現場では、大きなガラや石を粗くふるい分ける能力が求められます。
一方、伐採地や山土整地では、細かな有機物や粘土質のふるい分けが中心となります。
用途ごとに適した構造や性能が異なるため、目的と合わない機種を選ぶと作業が非効率になります。
まずは「何をどのように処理したいのか」を明確にしておくことが大切です。
土質や素材の性質もタイプ選定の決め手
扱う土の状態や混合物の種類も、選定に大きく関わります。
粘性土や湿った土が多い現場では、フィンガータイプやロータリータイプのような詰まりに強い構造が適しています。
一方、乾いた土や砂利混じりの素材には、振動式メッシュタイプなど粒度の調整がしやすいモデルが便利です。
素材の特性に合わないスクリーンを使うと、目詰まりや故障のリスクが高まり、作業の手戻りも発生します。
現場に搬入される残土や廃材の状態を事前に確認することが、適切な選定につながります。
処理量や移動頻度も忘れてはならないポイント
自走式スクリーンの運用には、1日の処理量や移動のしやすさも重要な判断材料です。
たとえば、複数の現場を回る運用を想定しているなら、コンパクトで運搬がしやすい機種が望ましいでしょう。
また、大量の処理が必要な現場では、高出力かつ連続稼働に耐えうるモデルが適しています。
加えて、メンテナンス性や操作のしやすさも確認しておくと、日々の作業がスムーズになります。
目先の価格やスペックだけでなく、実際の運用に即した視点で選ぶことが、長く使える1台を見つける鍵になります。
自走式スクリーンの種類を把握して、最適な一台を
現場の効率化やコスト削減を実現するには、自走式スクリーンの特性を理解し、用途に合った機種を選ぶことが重要です。
振動式と回転式にはそれぞれ異なる強みがあり、タイプごとに適した土質や作業内容が異なります。
たとえば、粗いふるい分けが必要な現場ではグリズリータイプ、粘土質や湿った素材にはフィンガーやロータリータイプが適しています。
「どれでも対応できる機種」よりも、「現場にぴったり合う1台」を選ぶ姿勢が、作業品質と生産性を左右します。
どのスクリーンを選べばよいか判断が難しい場合は、新西工業株式会社へぜひご相談ください。
現場の条件に合わせた最適な機種選定を丁寧にサポートいたします。

















