
建設現場では、建物の解体や工事のときにたくさんのゴミが出ます。
これを「産業廃棄物(産廃)」と呼びます。
産廃は、そのまま捨てるのではなく、種類ごとに分けてリサイクルできるものは再利用することが大切です。
そうすることで、環境を守ったり、廃棄にかかる費用を減らしたりできます。
しかし、現場での分別作業は「手間がかかる」「時間がかかって大変」「人も重機も必要でコストがかかる」と感じている方も多いでしょう。
そこで役に立つのが「自走式スクリーン」という機械です。
自走式スクリーンは現場の中を自由に動き回りながら、土やコンクリート、木材などのゴミを自動で分けてくれます。
分別作業が早くなり、無駄な運搬も減るので、現場の作業がとても効率よくなります。
この記事では、産廃の分別がなぜ大切なのか、そして自走式スクリーンがどうやって現場を助けるのか、わかりやすく説明します。
環境対策と経済性の両立を目指す建設事業者の皆様にとって、今後の事業戦略を考えるヒントになれば幸いです。
目次
循環型バリューチェーンとは?産業廃棄物管理の新常識
産業廃棄物の管理は、これまで「使ったら捨てる」という直線的な流れが一般的でした。
しかし、環境への配慮や資源の有効活用が求められる現代では、「循環型バリューチェーン」への転換が重要視されています。
循環型バリューチェーンとは、廃棄物をただ処分するのではなく、再資源化し、新たな価値を生み出す仕組みです。
国内外で環境規制やサステナビリティの要請が強まる中、企業はこの循環型モデルへの対応を迫られています。
これにより廃棄物管理のあり方が変わり、効率的で持続可能な産業廃棄物処理が求められるようになっているのです。
産業廃棄物とリサイクルの基礎知識
産業廃棄物を効率的に分別・再資源化するには、まずその性質や区分について正しく理解する必要があります。
特に建設現場では、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の違い、代表的な廃棄物の種類、そして分別を怠った場合に起こりうるコスト増加や法的リスクについて把握しておくことが重要です。
適切なリサイクル管理は、環境対策だけでなく企業経営にも直結します。
「一般」廃棄物と「産業」廃棄物の違い
廃棄物は大きく「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられます。
一般廃棄物とは、家庭から出るごみや、事業所から出る少量のごみを指し、市区町村が処理を担当します。
一方、建設現場や工場などから発生するごみは「産業廃棄物」に分類され、処理は排出した事業者の責任で行わなければなりません。
産業廃棄物には処理や運搬に関する厳しいルールが定められており、違反した場合は法的な罰則が科されます。
そのため、種類ごとの正しい分類と、適切な管理が非常に重要です。
(参考:環境省「一般廃棄物・産業廃棄物の区分について」)
代表的な産業廃棄物と再資源化の流れ
建設・解体現場では、「がれき類」「木くず」「汚泥」「廃プラスチック」などが主な産業廃棄物です。
これらは分別の精度によって再資源化率が大きく変わります。
例えば、がれき類は破砕して再生砕石として道路工事に利用できますし、木くずはチップ化して燃料や合板材料になります。
こうした再資源化のためには、現場での分別精度が非常に重要であり、その効率を高めるツールがスクリーン機です。
分別が不十分な場合のコストとリスク
廃棄物をきちんと分けていないと、混合廃棄物として扱われてしまい、リサイクルが難しくなります。
「混合廃棄物」とは、複数種類の廃棄物が分別されないまま混ざった状態の廃棄物のことです。
混合廃棄物は、処分費用が高くなるうえ、リサイクル率の低下によって企業の印象が悪くなるおそれもあります。
また、建設リサイクル法や廃棄物処理法に違反した場合、行政からの指導や罰則につながるケースもあるため注意が必要です。
(参考:環境省「建設リサイクル法の概要」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」)
一方で、しっかりと分別できていれば、処理コストを抑えながら資源を有効に活用することができます。
さらに、法律を守っているという安心感にもつながります。
なぜ“分別”が最初の一歩なのか
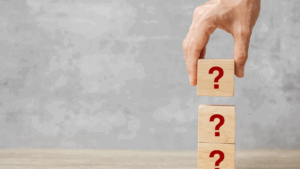
産業廃棄物の効率的なリサイクルを進めるには、まず分別が欠かせません。
混合廃棄物では再資源化率が大幅に下がり、処理の効率が悪化します。
分別が不十分だと、再利用可能な資源も廃棄物として処理されてしまうため、環境負荷が増すだけでなく、処理コストも高くなります。
たとえば、建設現場で分別を徹底するとCO₂排出量の削減につながります。
廃棄物を適切に分類すれば、運搬回数が減り燃料消費が抑えられるからです。
加えて、処理費用の削減効果も大きく、トータルでコストカットが可能です。
近年では、ESG(環境・社会・ガバナンス)レポーティングの重要性が増しています。
ESGレポーティングとは、企業や組織が「環境(Environment)」「社会(Social)」「ガバナンス(Governance)」の3つの観点についての取り組みや成果を報告する活動のことです。
そのため、「マテリアルフロー可視化」と呼ばれる廃棄物の流れを詳細に把握する技術が注目されています。
分別データを正確に管理することで、環境負荷を数値化し、企業の持続可能な取り組みを示せるようになるのです。
このように、分別はリサイクル成功の出発点であると同時に、企業価値の向上にも直結します。
スクリーン(ふるい機)による分別メカニズム
スクリーン(ふるい機)は、廃棄物の粒径に応じて分別を行う機械で、網目と振動を利用して素材を仕分けます。
振動によって廃棄物を動かし、サイズごとに分類するため、手作業よりも正確で効率的に分別できます。
細かい粒子から大きな破片まで、粒径ごとに分けることが可能で、再資源化に適した形に整える役割を果たします。
スクリーンの主な種類
スクリーンには主にディスク式とロータリー式があります。
ディスク式は複数の回転ディスクが廃棄物をふるい分ける仕組みで、木くずや土砂の分別に適しています。
一方、ロータリー式は回転するドラム内部に網目があり、より均一にふるい分けが可能です。
用途に応じて選ぶことで、分別精度と作業効率の最適化が実現できます。
たとえば、細かい粒子の分離にはロータリー式が向いており、大量処理にはディスク式が適しています。
自走式スクリーンの登場
近年は、自走式スクリーンが建設現場で注目されています。
自走式とは機械自体が移動できるタイプのスクリーンで、現場内での廃棄物処理が可能です。
これにより、廃棄物を遠方の処理施設に運ぶ必要が減り、輸送コストやCO₂排出を大幅に削減できます。
現場で分別から積み込みまで行えるため、作業効率が向上し、人件費削減にもつながります。
この仕組みは分別作業の効率化と環境負荷軽減を両立する最新技術として、今後ますます普及が期待されています。
自走式スクリーン導入の3大メリット
自走式スクリーンを導入することで、現場の作業効率やコスト管理が大幅に改善されます。
主なメリットは「コスト削減」「作業効率アップ」「環境貢献の見える化」の3つです。
それぞれについて詳しく説明します。
コスト削減—運搬費・処分費・人件費の具体的削減幅
まず、コスト削減効果が大きい点です。
自走式スクリーンは現場内で廃棄物の分別を行うため、運搬回数を減らせます。
これにより運搬にかかる燃料費や人件費が削減され、処分費用も抑えられます。
例えば、運搬回数が1/3に減るケースもあり、全体のコストを30%以上カットした事例も報告されています。
作業効率UP—“ふるい+積み込み”同時進行が可能
次に、作業効率の向上です。
自走式スクリーンは振動ふるい機能に加え、積み込み作業も同時に進められます。
これにより、従来の分別と積み込みを別々に行う手間が省け、作業時間を大幅に短縮できます。
現場の人手不足解消や作業負担軽減にもつながります。
環境貢献の見える化—自治体入札や取引先評価へのプラス効果
最後に、環境貢献の可視化が可能になることです。
分別状況や処理データが正確に管理できるため、ESG(環境・社会・企業統治)対応のレポーティングに役立ちます。
これにより、自治体の入札評価や取引先からの信頼度が高まり、企業価値向上にも貢献します。
自走式スクリーンは単なる機械以上の価値をもたらします。
DXで広がるトレーサビリティとデータ連携

建設現場での産業廃棄物の分別を、より正確かつ効率的に行うためには、DXの活用が欠かせません。
DXとは「デジタルトランスフォーメーション」の略で、デジタル技術を使って、ビジネスや社会の仕組みを大きく変えることを指します。
特に、IoTやクラウド技術、ブロックチェーンを用いた情報の見える化は、コスト削減だけでなく、環境への貢献や信頼性向上にもつながります。
IoTセンサーで重量・粒径をリアルタイムで把握できる
まず、IoTセンサーを自走式スクリーンに搭載することで、分別された廃棄物の重量や粒の大きさ(粒径)をリアルタイムで計測できます。
loTセンサーとは現場の温度・湿度・位置・振動・人の動きなどの“データ”をセンサーで集めて、インターネット経由で送信する仕組みです。
これにより、どのくらいの量の資源がどのように分類されているかが一目で分かり、手作業による集計や確認の手間が省けます。
これまで感覚で行っていた分別作業が、数字で「見える」ようになるのです。
クラウド×ブロックチェーンでデータを安全に管理・共有
計測したデータは、クラウド上に自動で保存されます。
さらに、ブロックチェーン技術を活用することで、その情報の改ざんができなくなり、安全に記録を残せます。
ブロックチェーン技術とは、取引データを改ざんできないように記録・管理する仕組みのことです。
これにより、自治体や元請業者との情報共有がスムーズになり、環境対応や監査の際にも信頼性の高い資料として活用できます。
廃棄物データはLCAやCO₂排出管理にも役立つ
さらに、こうしたデータは、製品のライフサイクルアセスメント(LCA)やサプライチェーン全体のCO₂排出量の管理にも活かされます。
つまり、スクリーン分別によって得られた情報が、企業全体の環境戦略の一部として機能するのです。
導入ステップと補助金・法規制チェックリスト
自走式スクリーンの導入を成功させるためには、段階的な準備と正確な法対応が欠かせません。
さらに、コストを抑えるための補助金活用や社内運用体制の整備も重要です。
ここからは、導入までの5つのステップをわかりやすく解説します。
ステップ① 現状排出量の測定とマテリアルバランス分析
まず着手すべきは、現場で発生している産業廃棄物の種類や量を把握することです。
マテリアルバランス分析を行うことで、どの廃棄物が多く発生しているか、再資源化のポテンシャルがあるかなどを定量的に評価できます。
これにより、分別の優先順位や導入すべき設備の方向性が明確になります。
ステップ② スクリーン機種選定(処理量・設置条件で比較)
次に行うのが、処理量や現場条件に合ったスクリーン機の選定です。
例えば、狭小な都市部の現場であれば小型の自走式が適しており、大量処理が求められる工場併設型施設では大型機が有利です。
粒度調整の自由度や運搬性、メンテナンスのしやすさも比較のポイントとなります。
ステップ③ 補助金・税制優遇を活用
スクリーン導入には一定の初期投資がかかるため、国や自治体の補助制度を活用することでコストを抑えられます。
たとえば「事業再構築補助金」や「エコリース促進事業」は、環境配慮型設備の導入を後押しする制度です。
補助要件やスケジュールを早めに確認し、申請書類を整備しましょう。
ステップ④ 法令・許可を確実に確認
廃棄物の処理には、「廃棄物処理法」「建設リサイクル法」「特別管理産業廃棄物に関する規制」など、複数の法規制が関わります。
導入する機械の用途や、分別後の搬出・再資源化方法によって必要な許可や届け出が異なるため、事前に専門家に相談することが推奨されます。
ステップ⑤ 社内教育とPDCA運用体制の整備
スクリーンを導入しただけでは成果は出ません。
運用担当者の教育やマニュアル整備が不可欠です。
また、分別結果や作業時間、処理コストなどを定期的に記録し、改善を繰り返すPDCAサイクルを構築することで、継続的な効率化と環境負荷の低減が実現できます。
社内全体での理解と協力も重要です。
成功事例:建設系A社が実現したコスト30%削減
自走式スクリーンの導入によって、建設系A社では産廃分別の効率が劇的に向上し、全体コストの30%削減に成功しました。
以下は、A社の具体的な取り組みと成果です。
混合廃棄物の割合を80%から20%へ削減
従来の現場では、ほとんどの廃棄物が混合状態で処理されていました。
その割合は実に80%。この状態では再資源化が難しく、最終処分費用も膨らみがちです。
しかし、自走式スクリーンを導入したことで現場での即時分別が可能になり、資源ごとのふるい分けが徹底されました。
その結果、混合廃棄物の比率はわずか20%まで減少しました。
再生材としての再利用や、中間処理業者の選定幅が広がり、コストを大幅に抑えることができました。
運搬回数を1/3に削減し、作業時間も短縮
分別の精度が上がったことで、無駄な運搬が減少しました。
混合廃棄物として一括で外部に運び出す必要がなくなり、資材ごとに効率よく処理先へ送ることができました。
結果として、トラックの運搬回数は従来の3分の1にまで削減。
これにより、燃料代や人件費も抑えられ、現場の作業負担も軽くなりました。
排出証明書とブロックチェーン活用で入札評価が向上
A社ではさらに一歩進んだ取り組みとして、廃棄物の排出証明をブロックチェーン技術で管理しました。
誰でも改ざん不可の形で「いつ・どこで・どのような廃棄物が・どこへ行ったか」を証明できる仕組みを構築しました。
これにより、自治体や発注元からの信頼性が高まり、公共工事の入札における評価も向上しました。
ESG(環境・社会・ガバナンス)対応を重視する時代の要請にも応える形となっています。
まとめ:――スクリーンで切り拓く循環型未来
循環型社会の実現には、廃棄物を「資源」として捉える視点が欠かせません。
中でも、自走式スクリーンを活用した分別は、DXによる可視化を経て、バリューチェーン全体の広がりにつながります。
まずは自社の廃棄物排出量や分別状況を把握し、小さな改善から始めてみましょう。現場単位の変化が、企業全体の持続可能性を大きく後押しします。
新西工業株式会社が選ばれる理由

新西工業株式会社は、自走式スクリーンのレンタルサービスを提供しています。
導入時には現場診断を行い、最適な機種をご提案。
さらに、導入後も専門スタッフが丁寧にサポートします。
建設・解体・土木など100社超の現場で導入実績があり、平均で28%のコスト削減に貢献しています。
まずは「公式サイト」からお問い合わせください。

















