
「建設現場で出る混合廃棄物(混廃)の扱いに日々悩んでいる」
「適切な分別方法がわからず、余計な処分費がかかっていると感じている」
このように悩む方は少なくないです。
当記事では、混合廃棄物の分別方法や処理費用の削減方法などを解説していきます。
混合廃棄物の適切な分別方法を知り、処理費用削減に役立ててください。
目次
混合廃棄物とは?
混合廃棄物とは、複数の種類の廃棄物が混ざった状態で排出されたものを指します。
建設現場などでよく見られる廃棄物で、「混廃(こんぱい)」という略称で呼ばれることもあります。
特に建設業では、木くず・コンクリートがら・プラスチック・紙・金属など、多様な資材が同時に廃棄されるケースがほとんどです。
たとえば解体工事の際に出るごみの中には、木材と金属が一緒になっているものや、ビニール養生と紙くずが混ざっているものなどがあります。
こうした混合状態のまま処理場へ持ち込むと、処理業者側での選別作業が発生するため、処分費用が高くなる上に、リサイクル率も下がるというデメリットがあります。
つまり混合廃棄物とは「複数の廃棄物が分別されていない状態」であり、コストや法令対応、環境配慮の面でも注意が必要なごみです。
現場での分別の徹底が、効率的かつ適正な廃棄物処理への第一歩といえるでしょう。
混合廃棄物の種類
混合廃棄物は主に以下の3種類に分けられます。
- 安定型混合廃棄物
- 管理型混合廃棄物
- 建設混合廃棄物
種類によって該当する廃棄物の品目や最終処分の方法が異なります。
それぞれの特徴を詳しく解説します。
安定型混合廃棄物
安定型混合廃棄物とは、環境への影響が少なく、最終的に埋立処分が可能な廃棄物のことを指します。
腐敗したり有害物質を出したりしない「化学的に安定したもの」で構成されており、廃棄物処理の中でも比較的扱いやすい分類に入ります。
そのため処理費用を抑えたい建設現場などでは、安定型混合廃棄物として処分できるかどうかはコスト管理に大きな影響を与えます。
具体的には、以下のような品目が安定型混合廃棄物に該当します。
- 廃プラスチック類(※汚れや油分の付着がないものに限る)
- ゴムくず(タイヤやゴムマットなど)
- 金属くず(鉄・アルミなど。ただし鉛を含むものは除く)
- ガラスくずや陶磁器くず(例:タイル、ガラス板、便器など。ブラウン管の一部を除く)
- がれき類(コンクリートがら、アスファルトコンクリートなど)
ここで重要なのは、「これらの品目だけ」で構成されている必要があるという点です。
つまりこれらの安定型品目の中に、たとえば木くずや紙くず、繊維、汚泥などが少しでも混入してしまうと、もう「安定型混合廃棄物」とは認められません。
その場合、より処理基準の厳しい「管理型混合廃棄物」として扱われ、埋立ではなく中間処理が必要になったり、処分費が高くなったりするリスクがあります。
安定型混合廃棄物として適正に処理するには、現場での確実な分別が不可欠です。
見た目が似ていても処理区分が異なる廃棄物は多く、担当者が基準を理解していないと、コスト増や処分業者とのトラブルにつながる可能性があります。
現場ごとに品目チェックリストを作成し、作業員全体で分別ルールを徹底することが、安全かつ効率的な処理への近道です。
管理型混合廃棄物
管理型混合廃棄物とは、環境への悪影響を及ぼすおそれがあるため、厳重な管理のもとでしか埋立処分できない廃棄物のことを指します。
このタイプの廃棄物は、処分場で埋め立てた際に雨水などでしみ出る「浸出水」によって、周囲の土壌や水質を汚染してしまう可能性があります。
そのため管理型混合廃棄物は「管理型最終処分場」と呼ばれる、浸出水の処理設備が整った専門の施設でのみ埋立処理が許可されています。
なぜ注意が必要なのかというと、これらの廃棄物の中には、有害な物質や腐敗しやすい成分が含まれていることがあるからです。
たとえば、木くず・紙くず・繊維くず・汚泥・廃油などは、時間の経過とともに腐敗したり、化学反応を起こしたりして環境に悪影響を及ぼす可能性があります。
また特定の金属成分や溶剤が混入していると、地下水への影響も懸念されます。
こうした性質から、管理型混合廃棄物は特に取り扱いに注意が必要です。
もし安定型と誤って分類してしまうと、処分場での受け入れを拒否されるだけでなく、不法投棄や法令違反とみなされ、罰則や指導対象になる可能性もあります。
また適切な処理がされないまま環境に影響を及ぼす事態となれば、事業者としての社会的信頼を失うリスクも無視できません。
つまり、管理型混合廃棄物とは、環境保全の観点から「特別な管理が求められる廃棄物」であるという認識が不可欠です。
現場での分別作業においても「これは本当に安定型か? 管理型の要素が混じっていないか?」という視点で確認することが、適正処理とトラブル防止の第一歩となります。
建設混合廃棄物
建設混合廃棄物とは、建設現場で発生するさまざまな廃棄物が混ざり合った状態のものを指します。
建築・解体・改修工事などの現場では、多種多様な資材が使用され、それに伴ってさまざまな廃棄物が排出されます。
これらをきちんと分別せずにひとまとめにしたものが「建設混合廃棄物」です。
この建設混合廃棄物には、以下のような品目が含まれることが一般的です。
- 廃プラスチック類(ビニールシート、梱包材など)
- ゴムくず(防振ゴム、床材など)
- 金属くず(鉄筋、アルミサッシなど)
- ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず(タイル、ガラス片など)
- がれき類(解体による破片や残材)
- 木くず、紙くず(ベニヤ板、段ボール、養生材など)
このように、建設混合廃棄物にはさまざまな性質のものが混在しており、処理の際には分類に応じた対策が必要になります。
実はこの建設混合廃棄物も、さらに細かく2つの種類に分けられます。
・安定型建設系混合廃棄物
金属くず、がれき類、汚れていない廃プラスチックなど、「安定型廃棄物」だけで構成されているものです。
これらは化学的に安定しており、管理の難易度が低いため、安定型最終処分場での埋立処分が可能です。
・管理型建設系混合廃棄物
木くず、紙くず、繊維くずなど、腐敗や分解しやすい成分を含んでいる混合廃棄物です。
これらは適切に管理しないと悪臭や汚染の原因になるため、管理型最終処分場での厳重な処理が必要となります。
このように、建設混合廃棄物を分類することで、処理費用や方法が大きく変わるため、現場での初期分別が極めて重要になります。
処理コストを抑えたい場合は、できる限り「安定型」の品目だけを分けておき、他のものと混ぜないことがポイントです。
また分別が不十分なまま処理場へ持ち込むと、「管理型」として扱われてしまい、本来より高い処分費を請求されるケースもあるため注意が必要です。
建設混合廃棄物の正しい理解と分別の徹底は、コスト管理・環境対策・コンプライアンス遵守すべてに直結します。
混合廃棄物処理費用の相場
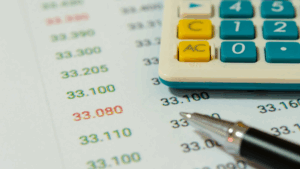
混合廃棄物の処理費用の相場は、種類・分別状況・量・地域・処分業者によって大きく異なります。
おおまかな相場の目安は、以下の通りです。
| 廃棄物の種類 | 処理単価の目安(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 安定型混合廃棄物(分別なし) | 15,000~25,000円/㎥ | 金属・がれき中心。比較的安価 |
| 管理型混合廃棄物(分別なし) | 25,000~40,000円/㎥ | 木くず・紙くずなどが含まれる場合 |
| 建設混合廃棄物(軽量系) | 20,000~35,000円/㎥ | 石膏ボード、断熱材など軽量物中心 |
| 建設混合廃棄物(重量系) | 18,000~30,000円/㎥ | コンクリート・タイルなど重量物中心 |
| 分別済み廃棄物 | 5,000~15,000円/㎥ | 種類により大幅に異なる |
分別がしっかりとされていたり、環境への影響も少ない安定型混合廃棄物は、比較的安価です。
また地域の差も大きく、都心など処分場の少ない地域では高価な場合が多いです。
混合廃棄物処理業者を選ぶ際のポイント
ここからは、混合廃棄物処理業者を選ぶポイントについて解説していきます。
混合廃棄物は種類によって処理方法も異なるため、注意が必要です。
適切な処理業者を選び、環境への配慮や法令に基づく処分をおこないましょう。
混合している全ての廃棄物の処理許可を取得
委託業者を選別する際、1番注意しなければいけないのが、混合している全ての廃棄物の処理許可を取得しているかどうかです。
廃棄物処理業者は、処理する廃棄物の種類ごとに「産業廃棄物処理業」の許可を取得しなければなりません。
廃棄物は性質や処理方法が異なるため、適切に処理できるように、廃棄物処理法で品目ごとの許可が義務付けられています。
誤った処理は、環境汚染や法令違反につながるリスクがあるためです。
例えば「木くずの許可しか持っていない業者」に「金属くず」が混ざった混合廃棄物を処理させると、法令違反になります。
(参考:環境省「廃棄物等の処理」)
近年、委託した廃棄物の中に許可の得ていない品目が含まれており、受け入れ不可になるケースも増えています。
委託業者を選ぶ際には、産業廃棄物処理業者の「許可証」や「許可品目一覧」を提示してもらうと安心です。
マニフェストの発行
廃棄物を処理する際、マニフェストの発行は必要不可欠です。
混合廃棄物のマニフェストは、基本的に「1部」で発行して問題ありません。ただし、記載内容には細心の注意が必要です。
混合廃棄物は複数の品目が一緒になっているため、「マニフェストの発行は品目ごとに分ける必要があるのでは?」と不安に思う方も多いでしょう。
しかし環境省の「産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度」によると、混合廃棄物として一括で処理される場合には、1枚のマニフェストで対応可能とされています。
ただし、マニフェストに記載する「廃棄物の名称」「種類」欄において、混合されている品目の詳細を明記することが義務付けられています。
(参考:環境省「産業廃棄物管理票制度の運用について」)
例えば、建設現場から出た混合廃棄物に「木くず」「金属くず」「廃プラスチック類」が含まれている場合、マニフェストの「産業廃棄物の名称」欄には単に「混合廃棄物」と書くのでは不十分です。
「木くず・金属くず・廃プラスチック類の混合物」など、具体的に含まれる品目を明記する必要があります。これを怠ると、処理業者や行政から不備を指摘されることもあります。
委託業者を選ぶ際には、マニフェストの交付を適切におこなってくれる業者を選びましょう。
混合廃棄物を分別する3ステップ

ここからは、混合廃棄物を分別する具体的な方法についてご紹介します。
①廃棄物の種類ごとに分ける
混合廃棄物は、一次分別として種類ごとに分けておくことがポイントです。
- 木くず
- 石膏ボード
- コンクリートがら
- 金属くず
- プラスチック類
- 紙くず
最初から種類ごとに分けておくことで、廃棄物処理のコスト削減になります。
②分別用コンテナや袋を現場に設置する
作業員がすぐに捨てられるように、分別用のBOXや大型フレコンバッグを複数配置します。
ラベルや色分けをしておくと、混合されにくくなります。
③分別ルールを周知する
作業員や協力会社にも「どの廃棄物はどこに捨てるか」を定期的に共有します。
新人にもわかるように写真付きの掲示物を作ると更に良いでしょう。
混合廃棄物を分別する5つのメリット
混合廃棄物を分別するメリットはコスト削減の他にもたくさんあります。
分別する5つのメリットについて解説していきます。
①コスト削減
混合廃棄物は処理工程が多いため、処分費が割高になります。
しかし、木くずやコンクリートがらなどを分別して出せば、1/2〜1/3程度にコストを抑えられるケースも多くあります。
出来るだけしっかりと分別することで、よりコスト削減につながります。
②リサイクル率の向上
混合廃棄物は適切に分別すれば、再資源化も可能です。
企業としての環境対応やSDGsアピールにもなるため、元請けや発注者からの信頼アップにもつながります。
③法令違反のリスク回避
廃棄物処理法では、適正処理・マニフェスト管理が義務づけられています。
混合廃棄物ばかりでは、違反リスクや指導対象になる可能性もあります。
そのため、できるだけ分別作業をおこなうことが大切です。
④作業現場の整理整頓
分別用のコンテナや袋を設けることで、廃棄物の置き場が明確になり、現場がスッキリします。
安全性向上や作業効率UPにも効果があります。
⑤処理業者とのトラブル防止
処理業者によっては、分別が不十分な混廃は受け入れ拒否されたり、追加費用を請求される場合もあります。
きちんと分別し、余計なトラブルは避けましょう。
混合廃棄物は「分ける」がコツ!
混合廃棄物は分けることで、コスト削減以外にもさまざまなメリットがあります。
新西工業株式会社では、現場でそのまま使える『自走式スクリーン』のレンタルサービスを提供しています。
この機械を使えば、コンクリートや土砂などの建設廃材を効率よく自動で分別できるため、分別作業の手間が大きく削減します。
是非一度、公式サイトで詳細をご覧ください。

















